三島由紀夫もタイやインドで仏教哲理を調べました。だが、いくら深遠であっても彼の納得できるものではなかったのでしょう。松枝清顕のホクロと「滝の下で会おう」の言葉は飯沼勲に継承されますが、勲の「南の国の薔薇の光の中で」はよくわかりません。ジン・ジャンにはホクロがなく、ただ同性愛の濡れ場の時にだけ浮び挙がるのです。四巻の安永透のホクロは偽物でした。三島は転生を一笑に付したのです。彼にとって「人生というものは奇妙なふわふわしたものであり、非現実的で一睡の夢のような」ものだったのです。
1970年11月25日の朝、新潮社の社員に「天人五衰」の最終稿を手渡して、三島由紀夫は市谷の東部方面総監部に出発します。彼の死の動機はなにか。「彼の天才がそうさせた」としか言いようがないのです。 凡々たる凡人の私は、天才にはついていけないことを痛感しました。まずお釈迦様の教えです。現代でも地球上には、目を覆いたくなるような事実が日々生起していることは理解できます。一方で私たちの境遇は大変恵まれていることも承知しています。だからこそ、生きている毎日は悲しみの連続ではなく、むしろ喜びや楽しさが多いと感じています。その喜び、その楽しさを、もっと広げていきたいと思うのはいけないことなのでしょうか? そんなことはありませんよね。贅沢三昧に耽って人々の顰蹙(ひんしゅく)をかうなんて論外ですが、みんなが幸せにあるよう努力するのはいいことだと思うのです。
私の職業は皮膚科専門医です。世の中の人々が健康で美しい肌を保っていただきたいと思って働いています。私自身もそうありたいと思って生きています。そしてずっと「美しさは表現ではなく意志です」と言ってきました。「美しくなりたい」の意志を挫けることなくもっていれば、美しさは保てます。まさしく持続可能、サスティナブルな意志です。あなたが美しくなれば、周囲の人は喜んでくれます。笑顔は平和をつくりだします。
私たちは天才にはなれません、凡人でしかありません。だから精進努力をしなければならないのだと思います。さぁ、来るべき新しい年に向かって、胸を張って歩いていきましょう!


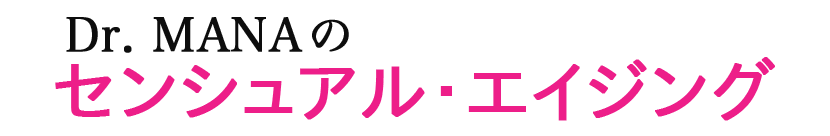

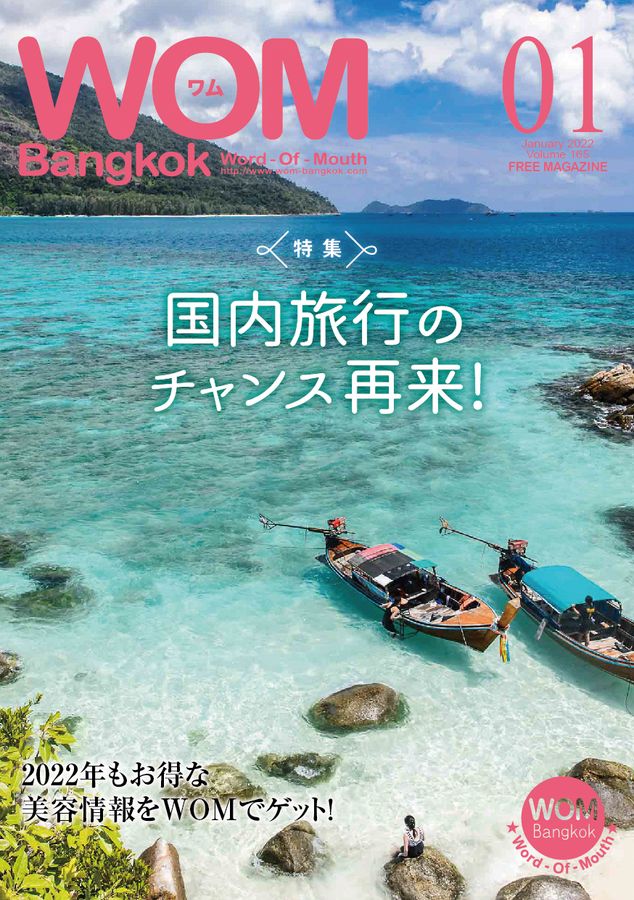


![VOL.198 ホアヒン旅行を楽しみつくす![前編]](https://www.wom-bangkok.com/wp-content/uploads/2024/09/v198-Cover.jpg)




