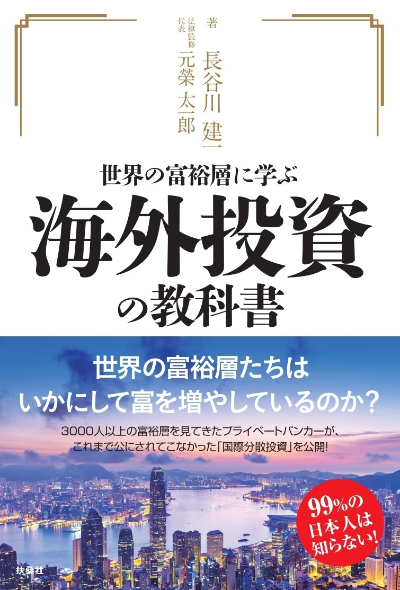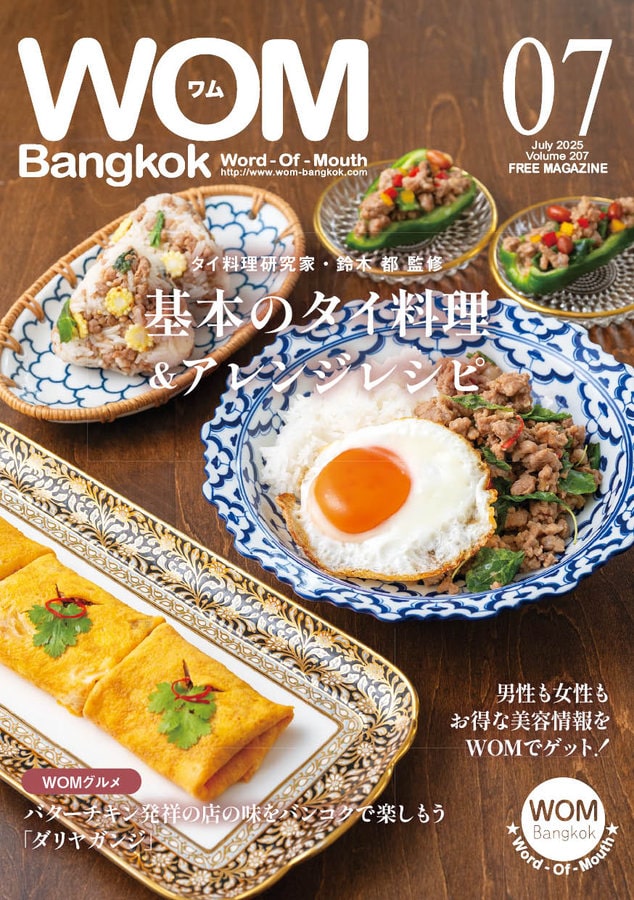コラム お金の知識を高めるコラム Vol.58 中国の『ゼロコロナ』政策が及ぼすリスク
Vol.58 中国の『ゼロコロナ』政策が及ぼすリスク

長谷川 建一
国際投資ストラテジスト
シティバンクグループ日本及びニューヨーク本店にて資金証券部門の要職を歴任後、シティバンク日本のリテール部門やプライベートバンク部門で活躍。 2004 年末に、東京三菱銀行(現三菱UFJ 銀行)に移籍し、リテール部門でマーケティング責任者、2009 年からは国際部門に移りアジアでのウエルスマネージメント事業戦略を率い2010 年には香港で同事業を立ち上げた。その後、2015 年香港でNippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank を創業。2020 年には、Wells Japan Holdingsに参画し、新たな金融サービスの開発に取り組んでいる。世界の投資商品や投資戦略、アジア事情に精通。わかりやすい解説には定評がある。香港をはじめ、日本やアジア各地での講演も多数。京都大学法学部卒・神戸大学経営学修士(MBA)
著書