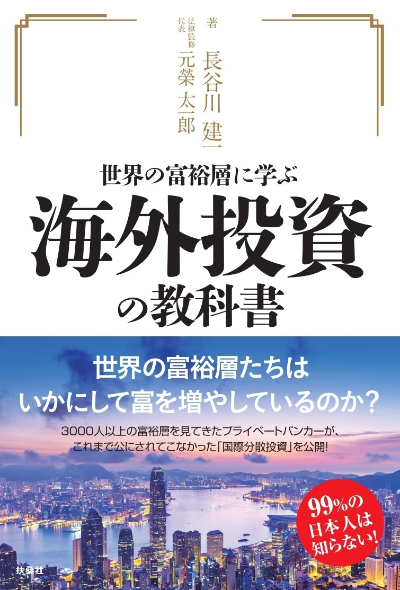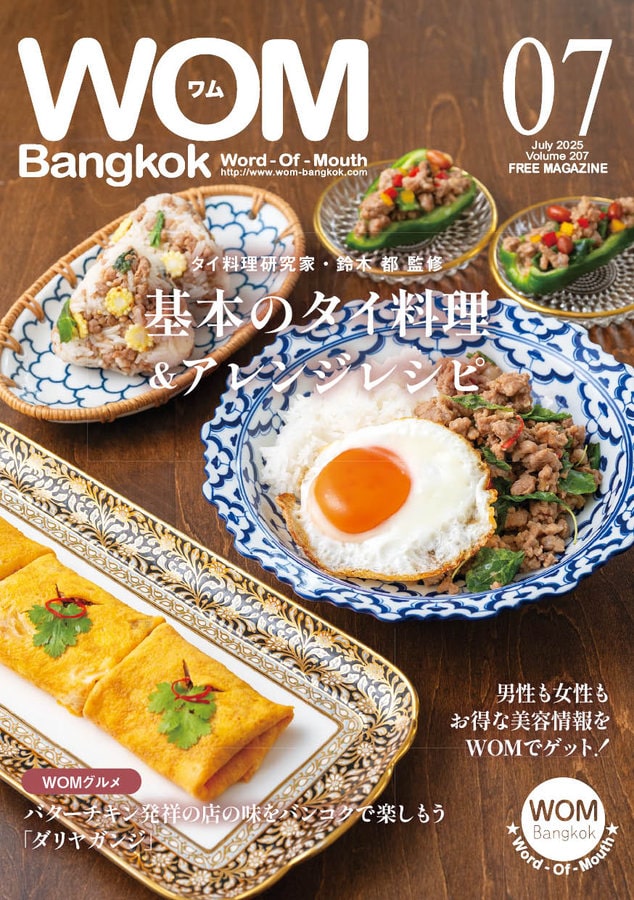「マイナス金利」という言葉をよく耳にしますが、金利がマイナスとはどういうことでしょう? 9月号で金利が低下する見通しについて書きました。米FRB、日銀、タイ銀行などはそれぞれ国の中央銀行です。「銀行の銀行」として金融機関への最後の貸し手として資金を供給し、政府の資金を管理する「政府の銀行」でもあります。中央銀行は国の金融・経済に関して独立した判断を下し、金融政策を実行することで物価の安定と経済の成長を図ります。
「マイナス金利」とは、金融機関が中央銀行に預けている預金の金利をマイナスにする金融緩和政策のひとつです。マイナス金利が適用されるのは金融機関が持つ日銀の当座預金の一部です。金利がマイナスなので、預金をしている金融機関は中央銀行から金利を受け取るのではなく、金利を支払うことになります。預金をしているのに金利も支払わなければいけない、つまり時間が経てば経つほど預金元本は減っていきます。
金融機関も、そんな預金なら預けたくはありません。出来るだけお金を口座に残さないよう、使おうとします。金融機関にとってお金を使うということは、お金を貸し出して金利を稼ぐこと、あるいは投資先を見つけて一定期間、投資するということです。しかし貸出先を見つけることが難しかったり、魅力的な投資先がなかったりすると口座にお金が残ってしまうのです。
「マイナス金利」は金融機関への一種のペナルティという考え方も出来ます。中央銀行からすれば、どんどんお金を使いなさいという政策なのですが、この状態が続くと金融機関の収益が細り、経営体力が弱って行きます。これがマイナス金利の弊害と呼ばれるものです。
日銀は、マイナス金利政策を2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」として導入しました。経済活性化とデフレ脱却を目指しての政策でしたが、効果が芳しくなく、景気に停滞感が拡がる中、追加緩和の検討も視野に入ってきました。
現在、「マイナス金利」政策は日本(日銀)とユーロ圏(ECB)で採用されています。ECBは、9月に包括的金融緩和政策を発表し、金利のマイナス度合いをより大きくしました。そしてついに欧州では、金融機関が預金者に対してマイナス金利分を転化する動きが出始めています。
自分の預金がマイナス金利の適用範囲になったらと考えると、ぞっとしますが、そんな事にも備えておかなくてはならない時代です。お金についてしっかりと考え、資産の運用について学びましょう。