金融市場では近頃、主要国の長期金利の上昇が目立っています。
いずれの国でもインフレ圧力が根強く緩和しないこと、軍事費や財政支出が増加していること、減税など拡張的な財政政策への懸念が拡大していることが共通項です。米・英・欧州とも債券市場で国債が売り込まれる現象が見られ、各国債の利回りはじわりと上昇し続けています。
米国ではトランプ税制改革法案が成立しました。これは減税が主となっており、財政赤字は短期的には膨らむ可能性が高いと見られています。欧州ではNATO首脳会議が軍事費の上限をGDP比で5%にまで引き上げることを決定しました。ロシアの軍拡に対応し、米国の要請に応える形での軍事予算引き上げは各国の財政に重い負担となります。EUのリーダーでもあるドイツは、長年守ってきた財政規律を堅持する憲法まで変更して財政の出動余地を拡大しました。
日本でも超長期日本国債の利回りは急ピッチで上昇しています。特に参院選を控え、与党で参院過半数割れの劣勢が報じられる中、野党主導の拡張的な財政政策への傾斜観測が、財政赤字拡大リスクを織り込ませる形で利回りの上昇圧力につながっています。
そして、日本では物価の上昇圧力も目立ってきています。代表的な事象はコメ価格の高騰ですが、食料品価格は全般に上昇しています。2025年度の生鮮食品を除く消費者物価指数(CPI)の上昇率は想定をかなり上回っており、日本銀行の物価見通しは上方修正される可能性が取り沙汰されています。
物価見通しの上振れは日銀の早期利上げを後押しする理由となります。そうなると投資家は日本国債を買いづらくなります。この需給のアンバランスは償還までの期間が長い10年超の国債の利回りを押し上げています。
7月初め、20年日本国債利回りは2.625%、と2000年以来の高水準に達しました。新発30年日本国債利回りは3.165%、新発40年債利回りは3.495%と、これまでの相場水準から大きく上昇しました。金利の大幅な上昇は利払いの形で財政に跳ね返ってきます。2025年度の当初予算で国債費は28.2兆円と過去最大に膨らみました。財務省の試算で、2028年度に長期金利が2.5%まで上昇すると、利払い費は10.5兆円から16.1兆円に増えます。
そしてもう一つ不気味なことは円安です。日本円金利の上昇は円高方向への材料とされてきました。しかし、最近の円金利上昇、日米金利差の縮小、は円高の支援材料になっていません。円金利の上昇は、悪い材料として円安として消化される材料となるかもしれません。

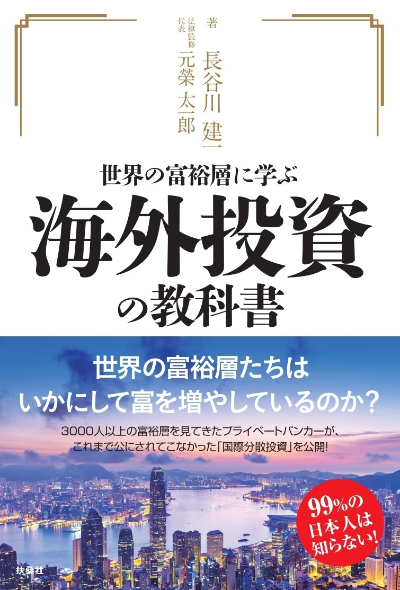



![VOL.208 そうだ、ピピ島に行こう[前編]](https://www.wom-bangkok.com/wp-content/uploads/2025/07/v208-Cover.jpg)







