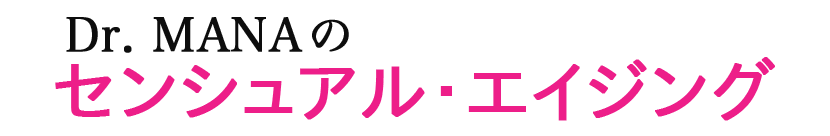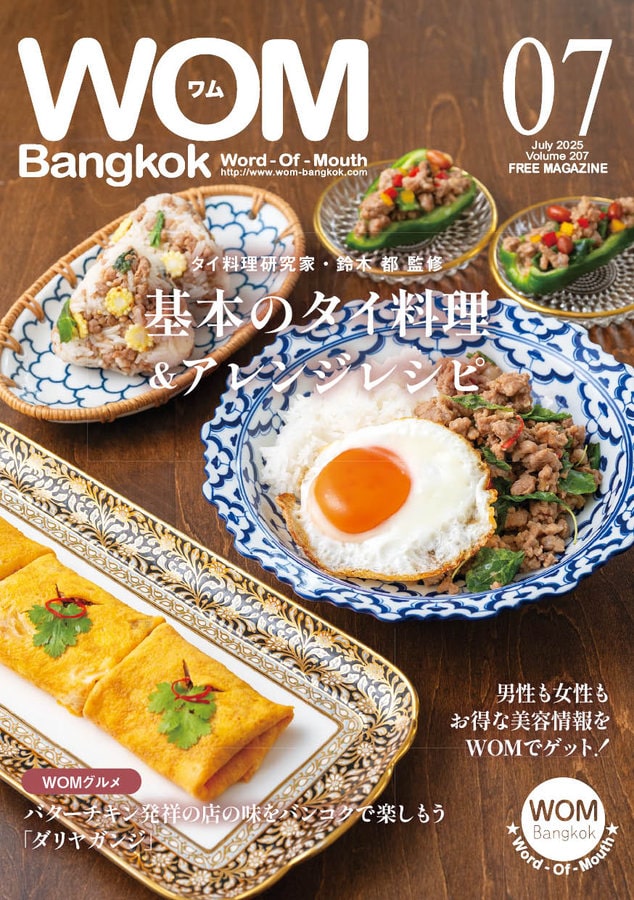バンコクの病院見学でまず驚いたのは、ロボット手術(ダ・ヴィンチ)の当たり前さ。もう2年前の話です。BDMS(バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス)やバムルンラードのような有名病院だけでなく、中規模の私立病院でも、婦人科や消化器系の手術にロボット支援が導入されています。しかも、AIと連携した手術室、術中モニタリングのリアルタイム可視化まで含めて、“未来感"が当たり前のように運用されているのです。
「え? ここってタイ? それとも10年後の日本?」本気でそんな言葉がこぼれました。
さらに衝撃だったのは「2台同時稼働はもう古い」と語る現地スタッフの一言。実際、da Vinci XiやXといった新機種への更新も進んでおり、研修体制や術者交代も想定されたプロトコルが整っている。若手医師が現場で“育てられる"仕組みが、すでに動いているのです。
一方、日本では2025年現在、ようやく2台目の導入がニュースになる病院もあります。
全国のda Vinci台数は570台超と世界有数ですが、その多くが泌尿器科に偏在。消化器・呼吸器・小児などの領域では、まだこれから。教育体制も、施設ごとの自主性に任されており、システムとしての統一感は薄いのが現状です。「日本の医療は進んでいる」と、私たちは無意識に信じてきました。でも実際は、電子カルテの連携も不十分、医療DXも立ち遅れ、慎重さが変化の足かせになっている部分も否めません。
バンコクで感じたのは、制度が整っていなくても“現場が動けば医療も進化する"という事実です。新しい技術を“使いこなす文化"があり、そこに“変化を求める空気"がある。だからこそ、変化が起きる。
もちろん、日本の医療には丁寧さや安全性、信頼という強みがあります。でもその慎重さが、結果として救命の遅延になってしまったら?私たちに必要なのは、技術を持つことだけではありません。「問いかける力」や「未来を想像する目」なのだと思います。「これ、日本でもできるんじゃない?」そんな一言が、未来を動かす力になると、私は信じています。
ここバンコクの医療は、きっと“未来のリハーサル"なのです。そしてそのリハーサルに、私たちはもう参加していい時代に入っているのかもしれません。